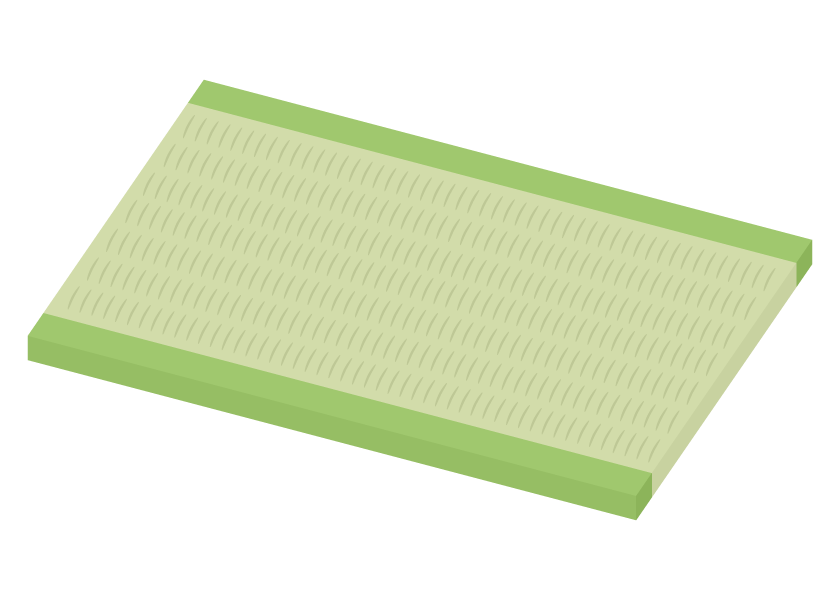
起きて半畳、寝て一畳(単位の話)
2025.02.02
こんにちは。|平屋|スタンドバイホーム長岡 代表の間嶋です。
「起きて半畳、寝て一畳」という言葉をご存知ですか?
人が必要な広さは、起きているときは半畳(畳半分)、寝るときは一畳(畳1枚)あれば十分。それ以上の贅沢は慎むべきという教えです。
畳はもともと、単体のマットのように使われ、偉い人が座るためのものでした。必要に応じて移動させるものであり、現代のように部屋全体に敷き詰めるものではありませんでした。
鎌倉・室町時代になると、武家屋敷や寺院などで部屋全体に畳が敷かれるようになり、建築の基準としての役割を果たすようになります。
安土桃山・江戸時代になると武士や町人の家も畳敷きが一般的になり、畳のサイズも固定化され、間取りの基準として定着しました。
その後、現代に至るまで畳のサイズが間取りの基準となり、「◯畳の部屋」というようになりました。
今では子ども部屋でも6畳が一般的かと思いますが、私が学生時代に最初に下宿をしていたのは3畳の部屋でした。
杉並区高円寺の一般のお宅で、2階が学生向けの下宿部屋になっていました。朝晩2食の賄い付きで、家賃は確か4万5千円程度だったと思います。お風呂はなく、洗面器に石鹸とタオルを入れて近くの銭湯へ通ったものです。部屋にはファンシーケース(ビニールロッカー)と小さいコタツ。布団を敷くとほぼ部屋は埋まります。
※(注釈)ファンシーケースというのは昭和の頃に爆発的にヒットした商品です。スチール製のパイプにビニールカバーをかけたもので、当時は友だちの家へ行くと必ずありました。
その頃、北区滝野川に友だちがいまして、遊びに行ったらなんと4畳半の部屋で、ものすごく羨ましいと思ったものです。1980年頃の話です。
高円寺にいたのは1年だけで、その後は埼玉県和光市のアパートに住む友だちから、「4年生が卒業するので6畳の部屋が空く」と教えてもらい、そちらに引っ越しました。一応1Kで、小さいシンクとガスコンロが1つだけついている部屋でしたが、広々として天国のようでした。
昔話に脱線してしまいましたが、日本の家は畳の大きさを基準に部屋の大きさが決まっています。エアコンや暖房器具、照明器具なども「◯畳用」という表示がされており、部屋の広さに合わせて選べるようになっています。
一方で、土地の面積は「坪」という単位になります。1坪=約3.3㎡=畳2枚分です。
もともとは中国の「歩」(ぶ)という面積の単位が日本に伝わり、日本では1歩=6尺×6尺(約3.3㎡)となり、後にこれが「坪」と呼ばれるようになりました。奈良時代のことのようです。
明治時代になると西洋の度量衡(どりょうこう)が入ってきて、メートルという単位が登場しますが、坪という単位は現在でも広く使われています。建築の世界では依然として尺貫法が使われていましたが、1891年の度量衡法の制定で尺貫法とメートル法とが併用されるようになりました。1951年になると計量法が制定され尺貫法は廃止。メートルという国際単位系で統一されました。公式な書類では「m」や「㎡」が使われ、それ以外の使用は禁止されています。余談ですが、計量法に違反をすると50万円以下の罰金もしくは6ヶ月以下の懲役という罰則があります。
そんな理由で、分譲地の広告や建売住宅の床面積には「◯㎡(△坪)」という表記が併用されています。
1メートルという単位は地球の大きさから決められました。赤道から北極までの子午線(経線)の長さの1000万分の1を1メートルとするというのが最初の決まりごとです。19世紀にはメートル原器が作られましたが誤差が生じるので、現在は光の速さと時間で1メートルが定義されています。真空中で光が2億9979万2458分の1秒間に進む距離だそうです。全然わかりません。(汗)
一方で畳の長い方の辺の長さは1間(いっけん)と呼び、6尺です。では、尺の起源はというと、手のひらを広げたときの親指と中指の先の長さ(約18cm)を1尺としたのが始まりのようです。その後、時代を経て1尺=約30.3cmとなりました。つまり、尺や坪、畳の大きさや部屋の広さは、人を基準につくられた単位ということです。
日本において、人が住む家や土地に「坪」や「畳」(帖という場合もあります)という単位が今でも根強く使われているのは、人が基準だったことに理由があるのかもしれません。
信じるか信じないかはあなた次第です。
おわり
